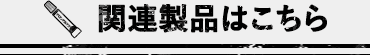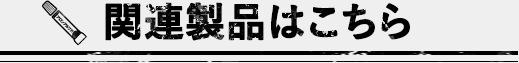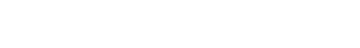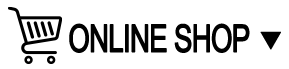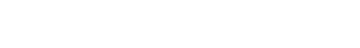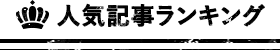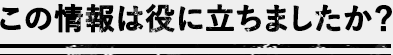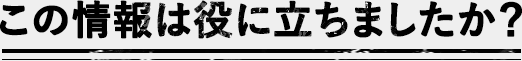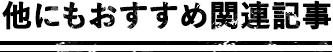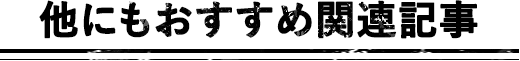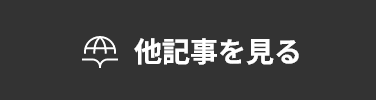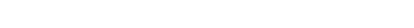
靴のかかとを自分で修理する方法を徹底解説!

靴のかかとが壊れてしまった経験はありませんか?お気に入りの靴や長く履いている靴は、知らないうちにかかとが傷んでしまっていることもありますよね。「自分で修理するのは難しそう」「どのようにすればよいか分からない」という方も多いのではないでしょうか。実は、靴のかかとは自分で修理できるケースも。
この記事では、靴のかかとの修理方法と、修理に必須の「靴用接着剤」について徹底解説します。
1.靴用接着剤を使った靴のかかとの修理方法
1-1.革靴・スニーカーのかかと|靴用接着剤で修理可能
1-1-1.かかとがすり減った場合
準備するもの
手順
1-1-2かかとが剥がれた場合
準備するもの
手順
1-2.ヒールのかかと|パーツ交換で修理可能
1-2-1.準備するもの
1-2-2.手順
1-3.靴の前底|専門業者に依頼を
2.靴のかかと修理のポイント
3.靴用接着剤の選び方
3-1.靴用接着剤とは?
3-2.靴のかかとの素材別・適した接着剤とは
3-3.着目すべき接着剤の特徴
4.靴用接着剤のおすすめ商品
4-1.シューグー X アロンアルフア
4-2.アロンアルフア EXTRAゼリー状
5.靴用接着剤の使い方
5-1.使い方
5-2.コツ
5-3.注意点
5-4.その他知っておくと便利なこと
6.靴のかかとの劣化を防ぐコツ7つ
6-1.靴べらを使う
6-2.歩き方に気を配る
6-3.脱ぐ時はかかとを押さえる
6-4.定期的にブラッシングする
6-5.毎日同じ靴をはかない
6-6.シューキーパーを使う
6-7.サイズの合った靴をはく
7.まとめ
靴用接着剤を使った靴のかかとの修理方法
修理する際に必要なものや手順は、靴の種類ごとに異なります。
ここからは、革靴・スニーカー、ヒールのある靴の修理について解説します。
その靴に合った修理をすることが大切なので、まずはそれぞれの修理方法をしっかり確認しましょう。
革靴・スニーカーのかかと|靴用接着剤で修理可能
革靴・スニーカーは日常で利用することも多く、その分かかとがすり減ったり、剥がれたりしてしまう経験をする方も多いのではないでしょうか。
靴を買い換えてしまう方もいますが、修理はそれほど難しくありません。
まずは一度、ご自身での修理を検討してみてください。
かかとがすり減った場合
準備するもの
革靴・スニーカーのかかとのすり減りには以下のものを用意して修理しましょう。
・補修用ゴムパーツ
・紙やすり
・「シューグー×アロンアルフア」(または「アロンアルフア EXTRAゼリー状」)
・油性ペン
・新聞紙
補修用ゴムパーツは100円ショップなどで販売されており、靴底のすり減りを補修できます。これで長い間靴を履き続けることが可能です。
手順
革靴・スニーカーのかかとのすり減りは以下の手順で修理を行います。
①靴の下に新聞紙を敷いて靴底の汚れや水分を取り除く。
②接着面を平らにするために、すり減り部分を紙やすりで磨く。
③補修用ゴムパーツがフィットするように合わせ、フィットする箇所に油性ペンでマークをつける。
④シューグー×アロンアルフア(またはアロンアルフア EXTRAゼリー状)を使って貼り合わせる。
⑤余分な補修用ゴムパーツをカットし、紙やすりで整える。ゴムパーツの周りにシューグー×アロンアルフア(またはアロンアルフア EXTRAゼリー状)を塗って補強する。
アロンアルフアが床についてしまうのを防ぐために、作業用の際は新聞紙を敷きましょう。乾燥の時間は、商品に記載された接着時間に従い、乾いたら履いてみましょう。両足の高さに違和感がなければ修理完了です。
かかとが剥がれた場合
準備するもの
革靴・スニーカーのかかとの剥がれには以下のものを用意して修理しましょう。
・シューグー×アロンアルフア(またはアロンアルフア EXTRAゼリー状)
・スクレイパーまたは紙やすり
手順
革靴・スニーカーのかかとの剥がれは以下の手順で修理を行います。
①靴の下に新聞紙を敷いて接着していた面に残った接着剤や汚れをスクレイパーや紙やすりで落とす。
②よく乾燥させる。
③シューグー×アロンアルフア(またはアロンアルフア EXTRAゼリー状)を塗る。
④接着面同士を合わせて押さえる。
乾燥の時間は、商品に記載された接着時間に従いましょう。履いてみて、両足の高さに違和感がなければ修理完了です。
ヒールのかかと|パーツ交換で修理可能
ヒールの先端は、だいたいは針とゴムでできています。ヒールが壊れるといえば、ヒールが丸ごと取れてしまうほか、この先端の針が折れてしまうか、ゴムの部分がすり減るか、またはとれてしまうケースが多いでしょう。
ヒールは革靴・スニーカーよりも簡単に、しかも安く修理ができるため、ぜひチャレンジしてみてください。
以下では、ヒールの先端部分が取れたり、すり減ったりした場合の修理方法をご紹介します。
準備するもの
ヒールの修理には以下のものを用意しましょう。
・ペンチ
・新しいヒール先端部分(100円ショップや靴店などで購入可能)
・トンカチ
・シューグー×アロンアルフア(またはアロンアルフア EXTRAゼリー状)
・紙やすり
ちなみに、ヒールの先端のゴム部分は「リフト」という名前です。
手順
ヒールの修理は以下の手順で行います。

①もとのヒールの長さに合う新しいヒール先端部分(リフト)を用意する(▲写真参照)。
②ペンチで、すり減ったゴムのヒール先端部分をはさみ、もとの靴から取り外す。
③新しいリフトの針の部分を、靴本体の穴に差し込み、はみ出た部分を切り取る。
やることはたったこれだけです。ゴム部分のすり減りがひどいと、ゴム部分をはさんで取り外すのが難しい場合もあります。その場合は、ゴム部分をきれいに剥がした後、針の部分をはさんで少しずつ抜きましょう。
針を穴に差し込むときに、きついようであればトンカチを使って優しくたたき入れ、ゆるいときは接着剤で固定します。ここまで修理できたら一度履いてみて、左右の高さが合っていれば成功です。高さが違うときは、紙やすりで少しずつ削って調整するか、両足のリフトを交換して、高さを調節します。
ヒールが丸ごと取れてしまった場合は、シューグー×アロンアルフア(またはアロンアルフア EXTRAゼリー状)を使って応急処置が可能です。また、ヒールを覆っている素材に傷がついたり、剥がれてしまったりした場合は専門店に持ち込んだ方がきれいに仕上がります。
靴の前底|専門業者に依頼を
靴の前底、別名ハーフソールの修理は、専門業者に任せるほうがよいでしょう。靴底補修用 滑り止めシートを使って修理も可能ですが、自分でやると剥がれやすい、きれいに仕上がらないなどのリスクがあります。ご自身での修理を推奨しないのは、かかとや靴底と違い、前底は広い範囲で剥がれてしまうことが多いためです。また、前底は目につきやすい部分でもあります。
フォーマルな場で困らないためにも、プロに仕上げてもらうのがおすすめです。
靴のかかと修理のポイント

靴のかかと修理で最も重要なことは、接着面をきれいにすることです。汚れを取り除くことはもちろんですが、剥がれた面の古い接着剤をきれいに取り除かないと強度が出ません。
汚れを取り除くことは意外と簡単なのですが、多くの方は古い接着剤を取り除くことが面倒に感じてしまいがちです。
古い接着剤は少量なら紙やすりでも取り除けますが、しっかり残っている場合はスクレイパー(▲写真参照)がおすすめです。
靴用接着剤の選び方

靴用接着剤選びの基本は、補修したい場所の素材に対応しているかを確認すること。靴によく使われるゴム・木材・布・金属などに対応した接着剤がおすすめです。
靴用接着剤とは?
靴用接着剤とは、剥がれた靴底や破れた箇所、中敷きや裏ゴムの剥がれを補修するための接着剤。強力な接着力があり、一般の接着剤と比べて負担がかかっても剥がれにくいのが特徴です。
いくつか種類があるため、補修する箇所の素材に合わせて選ぶことが大切です。
靴底の剥がれ専用のものからつま先やアッパー部分にも使える汎用タイプまで、さまざまな商品があります。
靴のかかとの素材別・適した接着剤とは
靴底のかかとには、さまざまな素材が使用されています。
それぞれに最適な接着剤は異なるため、素材別に解説します。
①革
・動物の皮革をなめしたもの
・主に高級品に使用される素材
・繊細な素材であるため、靴用の専用接着剤がおすすめ
②合成素材
・合成ゴムや合成樹脂を成型したソール
・加工が容易で、費用が安い
・樹脂やゴムが使用されているため、それらを接着できる接着剤が最適
③スポンジ
・合成ゴムや合成樹脂を発泡し成型底
・軽く、弾力性に優れる
・ゴムや樹脂を溶かさない接着剤が最適
④ウレタン
・発泡したポリウレタン樹脂のソール
・軽く、耐摩耗性に優れる
・プラスチック製品に対応した接着剤が最適
⑤天然ゴム
・天然の生ゴムが原料
・ゴムの接着に対応した接着剤が最適
着目すべき接着剤の特徴
接着剤にはいくつかの着目すべきポイントがあります。修理したい靴に最適な接着剤を選ぶことが大切です。ここでは特に大きな2つのポイントをご紹介します。
・耐水性
耐水性の高い接着剤を選べば、水にぬれてまたすぐ剥がれるという心配がありません。雨の日に履かなくても、足裏からの汗などで靴は湿気を伴いやすいので、重要なポイントです。
・色
透明の接着剤は接着跡が目立たず、仮に補修している時にはみ出てしまっても目立ちにくいのがメリット。一方、黒いゴムになじみやすい黒ゴム専用接着剤など、色のついた靴用接着剤もあります。
靴用接着剤のおすすめ商品
靴用接着剤はたくさんの種類があります。ここからは、アロンアルフアシリーズの中から特に靴のかかと修理におすすめの接着剤を2つご紹介します。修理を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。
シューグー X アロンアルフア
「シューグー X アロンアルフア」は、靴底の剥がれやパーツが取れた際の緊急補修に使用できる靴用接着剤です。付属の補修用やすりで接着面を滑らかにすることで、強力接着を可能にします。
革靴のソールやヒールのゴム部分などにも使用でき、接着から数秒ほどで硬化します。
ゴム・革・木材・金属・プラスチックの接着に使用可能なので、修理だけでなくデコレーションなど幅広く使用可能です。
アロンアルフア EXTRAゼリー状
「アロンアルフア EXTRA ゼリー状」は、速く強くつくという特徴はそのままに、粘度が高いゼリータイプのため、たれにくくスムーズに作業できます。
しみ込みやすい素材や凸凹部分、垂直面の接着に効果的で、靴底、かかと部分の緊急補修はもちろん、以下の用途にも使用可能です。
・革小物の補修やレザークラフト
・DIYや木製家具の補修・リメイク
・陶器・磁器の補修
・ゴムパッキンや金属アクセサリーなどの補修・接着
修理に創作に、一家に一本あると便利な接着剤です。
靴用接着剤の使い方
接着剤にはそれぞれ正しい用法・用量があります。
自己流で使用してしまうと、本来の効果が発揮できません。
購入した接着剤の説明書をきちんと読んで、正しく使用しましょう。
ここからは、アロンアルフアの具体的な使い方を解説します。
使い方
①水分・汚れ・油分を拭き取る
布やブラシなどで、ほこりや汚れ、水分を取り除きます。
補修用ゴムを使う場合には、表面がきれいに見えても離型剤やワックスが浮き出ていることがあるため、やすりをかけるなどの表面処理をしておくことがとても大切です。
手の脂も接着に影響するため、接着面に手で触れないよう心がけましょう。
最も重要なポイントは、古い接着剤が残ったままだと強度が著しく低下するということ。
手間はかかりますが、きれいに取り除いておくことが必要です。
②少量を塗布し貼り合わせる
接着面の片面に少量塗布し、接着剤を薄く押し広げるように、接着面同士を貼り合わせます。10円玉の面積に対し、1滴が目安です。つけすぎると硬化が遅くなるだけでなく、はみ出した部分やその周辺が白くなる白化現象が起こることがあります。
③しばらく押さえる
貼り付けたあと、手でしばらく押さえて完了です。
靴底につける接着剤の量は、適量が見極めづらく、はみ出てしまったり足りなかったりする場合があります。
はみ出てしまった場合には、硬化促進剤を使用すれば、白化現象も起こらずきれいに固まるでしょう。
つけた接着剤の量が足りない場合には、別売りの極細ノズルを使用して液状のアロンアルフアを少量流し込む方法が有効です。
瞬間接着剤は空気中の水分とも反応して固まってしまいます。
使用後は必ずノズルをきれいにし、カチッと音が鳴るまで締めましょう。
開封後のアロンアルフアを長持ちさせるには、水・熱・光を避けられる冷蔵庫での保管がおすすめです。再度使用する際は、アロンアルフアを室温に戻してから使います。
コツ
きれいに接着するポイントは次の3つです。
①すき間や凸凹をなくす
接着面にすき間や凸凹ができないように、やすりなどで削りなめらかにします。
②広げず、そのまま貼り合わせる
アロンアルフアは、空気中の水分にも反応して素早く固まります。塗り広げるそばから硬化してしまうので、塗布したらそのまま貼り合わせましょう(ノズルで塗り広げると、ノズル先端に汚れが付いて、アロンアルフアが長持ちしにくくなります)。
③くっつけたいものを温める
温度が低いほど硬化が遅くなり、接着しにくくなります。
気温が低いときは、ドライヤーなどを使ってあらかじめ30~50℃程度に温めると効果的です。
注意点
靴底のゴムはそのまま接着して大丈夫ですが、革やナイロンなどの合成繊維はそのまま接着するとしみ込んでごわごわになってしまいます。気になる場合は、あらかじめ「アロンアルフア 専用硬化促進剤」を吹いておくとしみ込む量が減るため、ごわごわ感を防止できます。
また、アロンアルフアは繊維状の材料にしみこむと急激に硬化し、発熱することがあります。
やけどの恐れもあるので注意しましょう。
その他知っておくと便利なこと
アロンアルフアには、靴に関して他にも便利な活用法があります。
靴ひもの端がばらばらにほどけてきたときに、一滴たらしておくことでそれ以上にばらけることを防止してくれるのです。縫い目がほどけてきたときも同様です。
また、アロンアルフアを使用する際は、専用の剥がし液である、「アロンアルフア はがし隊」も持っておくとよいでしょう。アロンアルフア はがし隊は、はみ出したり、固化したりしたアロンアルフアを素早く溶かします。手についたアロンアルフアの除去も簡単です。
靴のかかとの劣化を防ぐコツ7つ
靴は大切に履いていれば長く使えます。特に革靴は、部品ごとに分解できる作りになっており、修理しながら履けば10年以上履き続けることも可能です。
歩き方や脱ぎ方、履き方などについてかかとの劣化を防ぐポイントを、7つ紹介します。
日頃から意識して、靴のかかとを傷めないようにしましょう。
靴べらを使う
1つ目は、靴べら、別名シューホーンを使うことです。靴のかかと部分は傷みやすい部分で、糸がほつれたり、靴の内側が破れたりすることが多々あります。無理に履こうとして、かかと部分が潰れてしまった経験はないでしょうか。そのような傷みは、シューホーンを使うことで防止できます。
携帯用のシューホーンを持ち歩けば出先での脱ぎ履きもスムーズです。
歩き方に気を配る
歩き方に気をつけることで、ある程度靴の傷みを抑えられます。地面に接する部分、つまりかかとやつま先は常に摩擦が生じるため、特に傷みやすいところです。
かかと部分は、内股の人は内側が、ガニ股の人は外側がすり減ります。靴底のすり減りを防止するには、正しい姿勢で歩くことが大切です。かかとから地面に着地し、足の親指と小指に均等に力を入れて蹴りだす、というイメージで歩いてみるとよいでしょう。
脱ぐ時はかかとを押さえる
靴を脱ぐ時は、手でかかと部分を押さえて脱ぐほうが、靴のかかとを傷めなくて済みます。よくやってしまうのは、手を使わずに、両足のかかとを擦り合わせながら靴を脱ぐ方法です。このような脱ぎ方をすると、こすれた部分や靴の内側が傷んでしまいます。ひも靴の場合は、軽くひもを緩め、無理な力をかけずに脱ぐことも大切です。
また、靴を履いているときにかかとを踏んでしまっている方もいます。頻繁に踏むとかかとの型が崩れてしまうため、脱ぐときだけでなく履くときもかかとには気を配りましょう。
定期的にブラッシングする
靴を履いた後は、縫い目やシワに沿って、全体をブラッシングしてください。1日履いた靴には、思っているよりも汚れやホコリがついています。こまめにブラッシングすることで、靴の劣化を防ぐことが可能です。あまり強くこすりすぎないように気をつけましょう。
ブラシにはやわらかい馬毛と、硬い豚毛のものがあります。ホコリ落としで使う際は馬毛のブラシが向いています。また、履いた靴は湿気も帯びているため、収納前に乾燥させるとよいでしょう。
毎日同じ靴をはかない
同じ靴を毎日履かないことも、靴のかかとの劣化を防ぐ方法のひとつです。連続で同じ靴を履いてしまうと、たまった湿気が抜け切れずに残ってしまいます。雑菌が繁殖しやすく、劣化につながるためよくありません。それを防ぐには何足か靴を用意しておき、毎日履き替えることが最適です。
最低でも1日、理想は2日、靴を休ませてください。履く頻度が減ると、かかとも長持ちします。3~4足あれば十分に靴を乾燥させる時間がとれるでしょう。
シューキーパーを使う
シューキーパーとは、靴を保管する際に、靴全体の型崩れを防ぐために入れる道具のことです。別名シューツリーともいいます。型崩れを防ぐ以外にも、靴底の反り返りや革のひび割れの防止、靴の履きじわ伸ばしなどの役目もあるのです。
さらに、木製のシューキーパーには除湿効果もあり、カビを防ぎます。また靴磨きなどお手入れ時にも、型崩れ防止のためにシューキーパーを利用するとよいでしょう。
サイズの合った靴をはく
サイズの合っていない靴を履いていると、靴の中で指を踏ん張ってしまうため、足に過剰な汗をかきます。それが原因で、靴の劣化が進んだり、大きな負荷がかかって、靴の寿命が短くなったりするのです。
サイズの合っていない靴は、足臭が発生する原因のひとつでもあります。また、身体のゆがみや外反母趾(し)、冷え性につながるリスクもあるため、注意が必要です。靴は、デザインばかりを重視して決めるのではなく、サイズがきちんと合うものを履くようにしましょう。
まとめ
靴のかかとは、意外と人から見られています。すり減りがないか、剥がれかけていないか、日常的に意識して確認することが大切です。靴のかかとの補修が必要になったときは、ここで紹介したアロンアルフアを利用して、ご自身で直してみてください。
修理の際は、靴の素材に合った適切なアロンアルフアを選ぶことが重要です。こまめにお手入れをすることで、大切な靴をより長く履き続けられますよ。